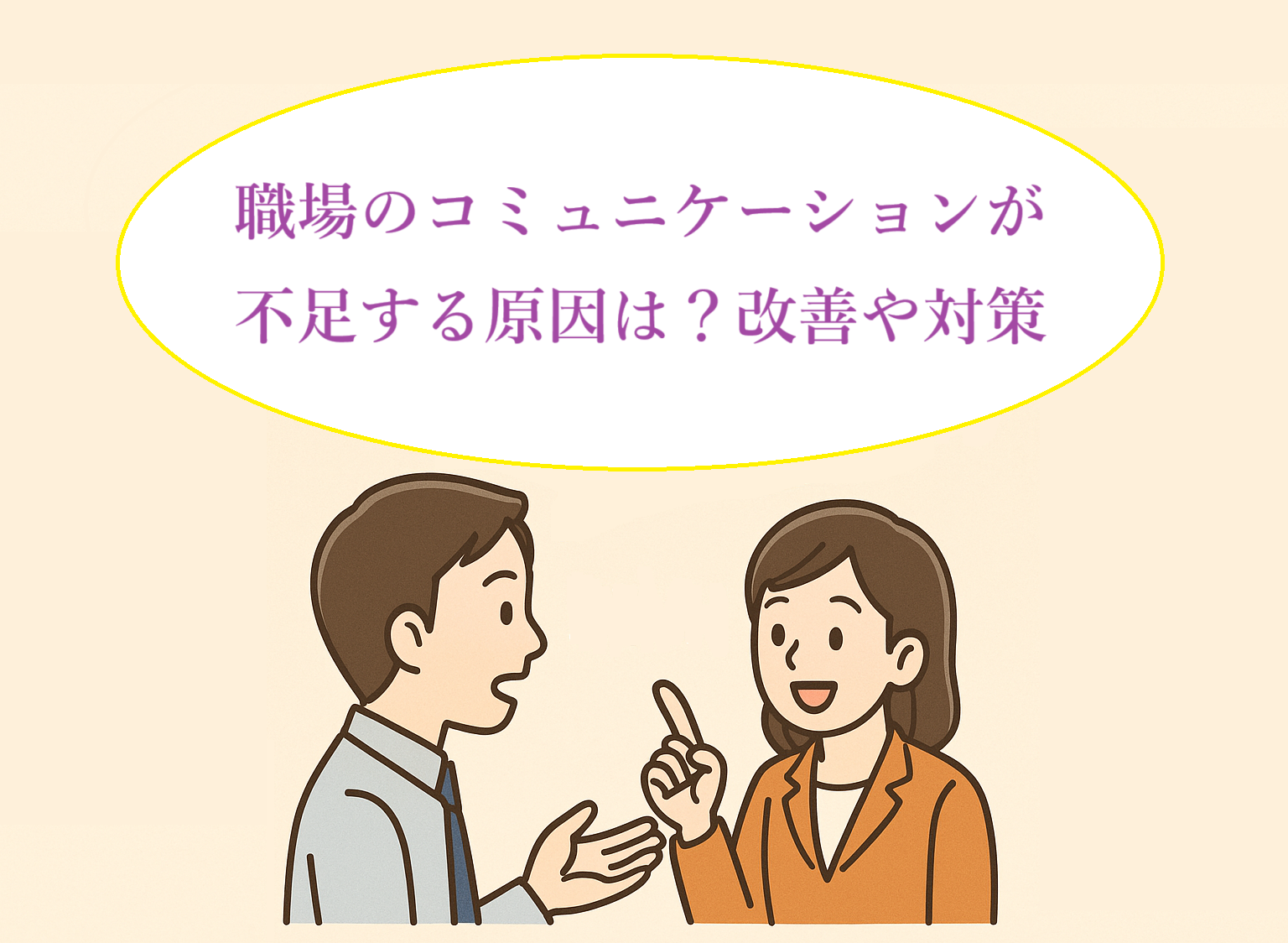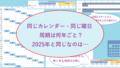コミュニケーション不足だと職場で感じて対策したいということもあるかもしれません。職場のチームワーク向上のためにも「上司とコミュニケーションが難しい」「部下とコミュニケーションが取れない」といったことは避けたいですよね。職場でのコミュニケーションの取り方としては、うまくいかない原因を把握して改善することが重要です。今回は、職場でのコミュニケーションを活性化させる方法を、筆者の経験を交えつつ、ノンバーバルコミュニケーションの種類や具体例とともにご紹介します。
◎職場のコミュニケーションが不足する原因は?改善や対策も
職場のコミュニケーションが不足するのにはどのような原因が考えられるのでしょうか。部下とコミュニケーションが取れない・難しいと課題に捉えているときには業務の忙しさで足りていないことがまず考えられます。仕事に追われると、必要最低限のやりとりしかできなくなりやすいです。また、上司と部下との距離感も要因の一つかもしれません。部下と上司のコミュニケーションでは世代や価値観の違いもありますし、同僚同士の間に質問や相談しにくい雰囲気があると、部下同士のコミュニケーションも滞る傾向があります。コミュニケーション不足が起こる職場の原因で最近多いのがリモートワークや飲み会の減少の影響です。オンラインでのやり取りが中心になると、最低限の報告や相談にとどまります。一見すると効率的かもしれませんが、雑談の機会が減ることで、上司と部下のコミュニケーションにギャップが生じやすくなり、より適切な業務の割り振りなど連携が取り辛くなるのです(筆者の入社当初の上司は取締役であり、そもそもビルが異なるなどの理由もあり、踏み込んだ会話をする機会はほとんどありませんでした)。

職場でのコミュニケーションの不足を改善するには、職場での原因ごとに対策を講じていくことがポイントになります。忙しい職場で上司とコミュニケーションが取れない・難しいと感じる場合は、短時間でも定期的に1対1のミーティングを設けるのが有効です。決まった時間を確保することで、報告や相談の機会が増え、部下の状況を把握しやすくなります。上司と部下のコミュニケーションにギャップや距離感が適切でない場合は、普段から意見を積極的に聞く姿勢を持つことが大切です。オープンな対話を増やすことで、信頼関係が築かれ、円滑なコミュニケーションにつながります。オンラインでのやり取りに関しては、朝礼など定期的に発言する場を設ける、気軽に質問できる環境を整えるといった工夫が効果的です。チーム力の強化・向上のためにコミュニケーションでどんなことを工夫できるかをみていきましょう。
◎職場でのコミュニケーションの取り方
職場でのコミュニケーションの取り方を工夫すると、業務の効率が向上し人間関係も良好になります。適切な伝え方を意識することで、誤解やトラブルを防ぎ円滑な協力体制を築くことができるからです。職場のチームワーク向上のために、「話しやすい雰囲気を作る」「相手の話を傾聴する」「フィードバックを適切に行う」ことが具体例として挙げられます。コミュニケーションが取れない部下や顧客との場合は特に注意が必要ですが、一方的に気持ちよく話せている状態ではうまく意思疎通ができていません。職場のコミュニケーションを活性化させるために、研修をもしするのであれば相手が話をする割合が7割くらいになるようしてみましょう。そのためには、相手が言ったことを受け入れて、5W1H(何・いつ・どこ・誰・なぜ・どうやって)などの返答しやすい質問を投げかけて話を拡げるのがおすすめです。
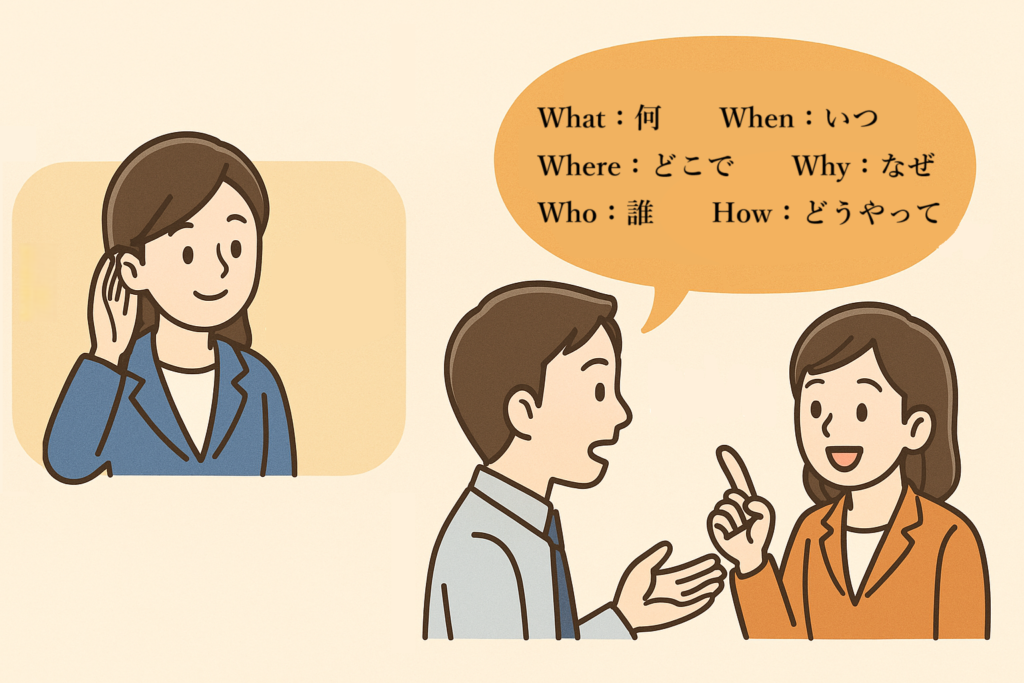
上司と部下のコミュニケーションの事例として、指示や評価はより具体的に伝えるように心がけましょう。「良かった」「ダメだった」といった曖昧な表現ではなく、「○○の対応が迅速で助かった」「この資料はもっと簡潔にまとめると伝わりやすい」などと客観的に見てどう評価・指示されているのかが明確なのがおすすめです。会う頻度が少ないなど、部下とコミュニケーションが取れない場合でも、日々の努力や成果をしっかり言葉で伝えることで、モチベーションの向上につながります。当方も職場のアルバイトとはほとんど話ができないこともありますが、退勤時には可能な限り「今日もありがとうございました」と一言だけでも伝えるようにしています。
◎上司と部下との距離感はどのくらいが適切なのか?
上司と部下との距離感はどのくらいが良いのかは悩ましいかもしれません。コミュニケーションが苦手な部下(積極的に取らない部下)は放置しすぎると相談しにくくなり、業務の効率が下がることも考えられます。逆に、部下とのコミュニケーションの取り方がフランクすぎると、業務上の緊張感が失われたり、信頼しすぎることで指示の伝達が曖昧になってしまうこともあるかもしれません。そのため、「仕事の話は真剣に、雑談は適度に」というメリハリを意識することが大切です。
上司と部下のコミュニケーションの方法としては、週に1回や月に1回など定期的に1対1で話す時間を設けることで、業務の進捗や悩みを共有しやすいです。「何か困っていることはない?」と聞くだけでなく、「最近の業務で一番大変だったことは?」「もっと改善したい点は?」と具体的に聞くことで、部下の意見を引き出しやすくなります。そして、ノンバーバルコミュニケーションを活用することの効果として、部下が話しやすい雰囲気を作れるなどがあります。非言語的なコミュニケーションにどのような具体例や種類があるのかは次の項目でみていきましょう。
◎ノンバーバルコミュニケーションの種類とは?具体例を紹介
ノンバーバルコミュニケーションとはどのようなものなのか気になるかもしれません。非言語のコミュニケーションとは、言葉を使わずに相手に情報や感情を伝える手段のことです。ノンバーバルコミュニケーションの種類としての具体例は、表情・ジェスチャー・視線・姿勢などが挙げられます。特に、非言語的コミュニケーションの効果の具体例として挙げられる表情や姿勢は、日常生活にも関係するもので、笑顔でうなずくことで相手に「話をしっかり聞いている」という印象を与えられます。逆に、腕を組んでしかめっ面で話を聞くと無意識のうちに「拒絶」のサインを送っていることになるでしょう。
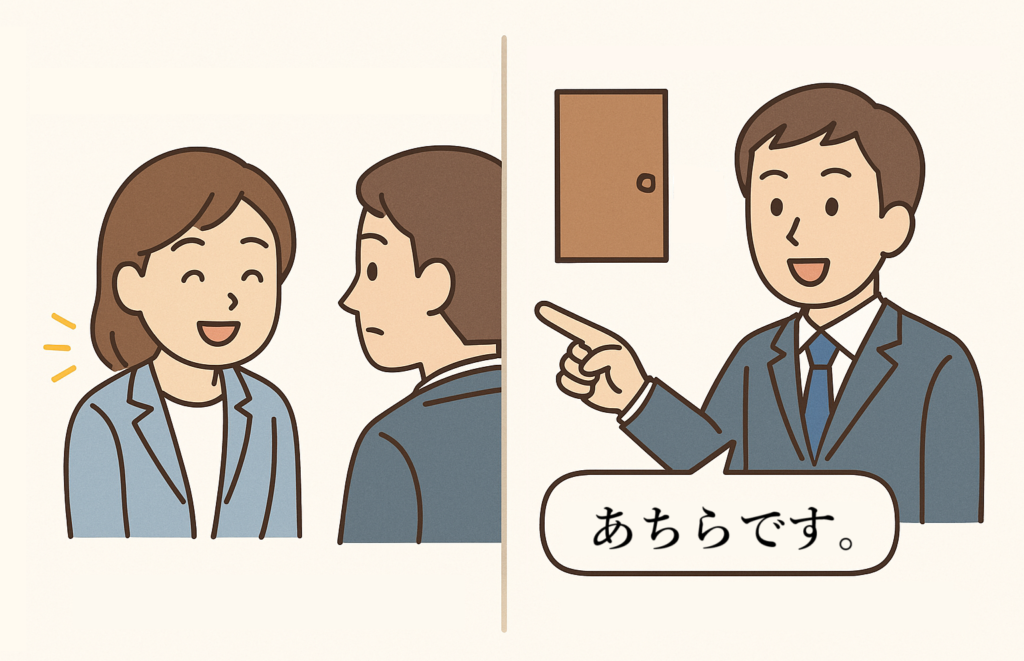
非言語コミュニケーションの能力は言語コミュニケーションと組み合わせることでより効果があります。例えば、非言語コミュニケーションの種類の例としてジェスチャーは、相手の注意をひいて言葉の補足をするのに役立つことも多いです。単純に「あちらです」「これにします」という言葉だけではなく、指をさすことで複数のものから選ぶあるいは方向を示すときに何なのかが明確になりますよね。また、言語コミュニケーションの種類を複数組み合わせることも効果があります。例えば、上司がゆっくりと落ち着いた声ではなく早口で話すと、部下はせかされている印象を受けてしまうかもしれません。このように、非言語コミュニケーションのメリットは、言葉を使わなくてもあるいは言葉と組み合わせることで気持ちを伝えられることにあります。
◎まとめ
今回は、職場のコミュニケーションが不足する原因や、改善のためにできることについてご紹介しました。コミュニケーション不足は、職場における業務の忙しさのほか、原因として世代間の価値観の違いによる距離感、関わる機会そのものの減少などが挙げられます。しかし、定期的なミーティングの実施や、意見を聞く姿勢を持つことで改善が可能です。円滑なやり取りができる環境を整え、チーム力の強化や向上のために非言語的コミュニケーションも利用して効果を高めていきましょう。最後までお読みいただきありがとうございました。